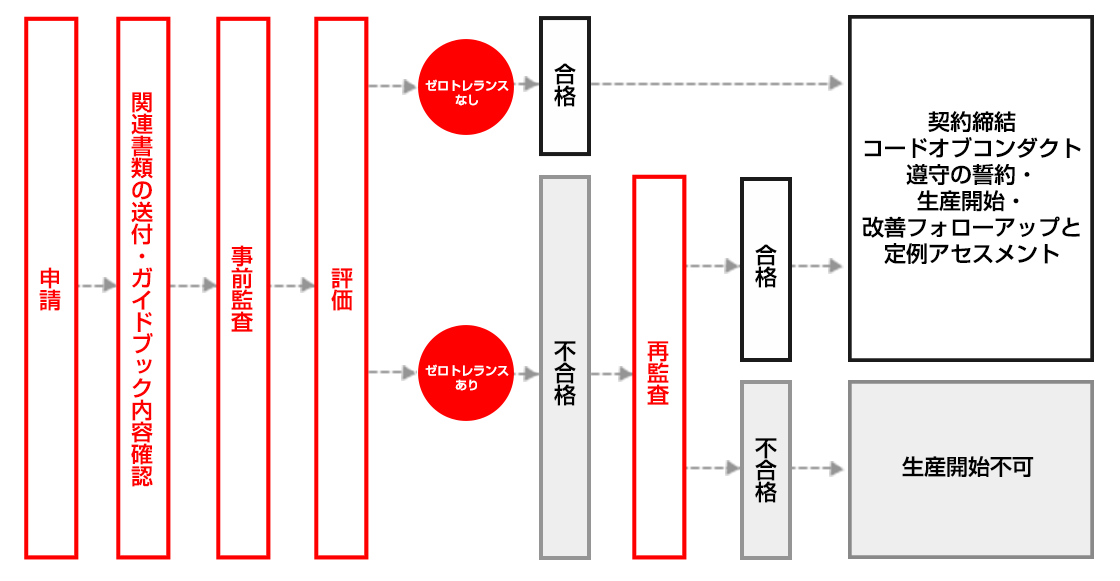最終更新日: 2026.02.06
to English page
サプライチェーンにおける人権の尊重や労働関連法令の遵守、労働環境の改善を最優先課題のひとつと考え、「生産パートナー コードオブコンダクト」に基づき、労働環境モニタリングに積極的に取り組んでいます。
労働環境モニタリングの概要
ファーストリテイリングは、2004年に「生産パートナー コードオブコンダクト」を策定し、2024年8月期はすべての縫製工場、主要素材工場、ユニクロ綿商品の主要紡績工場および一部の副資材工場を対象に、労働環境モニタリングを通じた遵守状況の確認を行っています。労働環境モニタリングのアセスメント手法として、第三者機関による抜き打ち監査や、アパレル・フットウェア業界共通のフレームワークによるアセスメントを導入しています。いずれの方法でも、ファーストリテイリングの労働環境基準に基づき工場の労働環境を評価し、リスクの深刻度に応じた改善活動を行っています。新規に取引を開始する縫製工場に対しては、事前監査を実施することで、適正な工場のスクリーニングを行うとともに、早期に労働環境の改善に着手できるようにしています。今後も原材料調達の最上流までを自社で把握し、自社従業員による訪問や第三者機関による監査、第三者認証などを通じて、バリューチェーンにおける人権の尊重や労働環境の改善の取り組みを進めていきます。
ファーストリテイリングは2015年、公正労働協会(FLA)に加盟しました。FLAの労働環境基準の導入のほか、労働環境モニタリングプログラムの改善、およびFLA加盟企業や工場、市民団体、労働組合などのステークホルダーとの対話について、FLAから支援を受けており、2019年2月にはFLA認定を取得しました。これは、労働環境モニタリングを含め、当社のサプライチェーンにおいてFLAの労働環境基準を満たすための仕組みや手続きが整備・運用されていることを意味しています。FLAは労働環境基準が継続して満たされているかを確認するため、毎年、サンプルベースで工場の監査を行っています。2025年8月期は、当社の生産パートナーのうち2工場が監査の対象となりました。
関連リンク
新規工場の事前監査
新規に取引を開始する縫製工場に対しては、ファーストリテイリングの基準に基づく事前監査を実施することで、適正な工場のスクリーニングを行うとともに、早期に労働環境の改善に着手できるようにしています。事前監査に合格し、「生産パートナー コードオブコンダクト」遵守を誓約いただける工場とのみ契約しています。2025年8月期は76工場が事前監査の対象となりました。その内、事前監査で不合格となったものの、改善のうえ再監査で合格した2工場を含め、65工場と「生産パートナー コードオブコンダクト」を締結し、取引を開始しました。
新規工場の承認プロセス
既存工場の定例アセスメント・モニタリング
ファーストリテイリングは、取引を開始した工場に対して、定期的な労働環境モニタリングを実施し、コードオブコンダクトの遵守状況を確認しています。
 労働環境モニタリングの仕組み*
労働環境モニタリングの仕組み*
*ベターワークの監査を実施している工場の評価・改善フローは、この限りではありません。
 アセスメントの手法
アセスメントの手法
ファーストリテイリングが求める労働環境基準を追及すると同時に、一つの工場に対して複数のブランドが独自の監査を行うことで生じる過剰な負担を減らし、工場による自主的な労働環境マネジメントシステムを強化するため、モニタリングプログラムの最適な設計を継続的に検討しています。現在、第三者機関による抜き打ち監査のほか、国際労働機関(ILO)と国際金融公社(IFC)の共同活動プログラム「ベターワーク」による監査を併用しています。いずれの方法でも、ファーストリテイリングの基準に基づき工場の労働環境を評価し、リスクの深刻度に応じた改善活動を行っています。
欧州で予定されている人権リスクの特定や予防プロセスの義務化を見据え、ファーストリテイリングでは、より効果的なリスク把握と監査品質の向上を目指し、2025年8月期から新しい監査プログラムを導入しました。従来の監査項目に加え、各国・各工場固有のリスクを反映した項目を設置し、工場のガバナンス機能・組織体制、工場から共有される情報の信頼性に対する監査項目も充実させ、従来より厳しい基準で工場の人権リスクを把握できる体制を構築しています。
なお、2025年8月期は、監査プログラムの移行期のため、一部の工場では旧監査*を実施しています。
* SLCPの自己評価・第三者検証、ベターワークの監査、第三者機関の抜き打ち監査
 ベターワークによる監査
ベターワークによる監査
一部の工場では、国際労働機関(ILO)と国際金融公社(IFC)の共同活動プログラム「ベターワーク」による監査を実施しています。アパレル業界で広く導入されているベターワークの監査を受けることで、工場は監査の重複を減らすことができ、労働環境の改善により注力することができます。
関連リンク
 第三者機関の抜き打ち監査
第三者機関の抜き打ち監査
ベターワークの監査の対象とならない工場は、第三者機関による抜き打ち監査の対象となります。監査は原則として年1回実施します。監査では、監査員が工場を訪問し、従業員代表、労働組合代表、経営者層などへのインタビュー、労働協約や契約書、給与明細、出勤簿、タイムカードといった諸記録のレビュー、現場視察による労働安全衛生状況などの確認を行います。宿舎がある場合は、宿舎も確認の対象となり、宿舎で労働者のインタビューを実施することもあります。監査のオープニングとクロージングの際には従業員代表や労働組合代表も参加し、労働者の声を評価に反映できるようにしています。
 監査項目と評価
監査項目と評価
2025年8月期に導入した新監査プログラムでは、監査対象となる工場の「生産パートナー コードオブコンダクト」の遵守状況をA評価からE評価の5段階で評価を行っています。
ファーストリテイリングは、著しく人権を侵害する問題に対してゼロトレランス方針を採用しており、重大な人権侵害を一切容認しません。重大な人権リスクがあり、リスク管理体制が不十分であることを意味するE評価に該当する場合には、速やかに是正措置や取引関係の見直しなど、厳正な対応を行います。E評価の対象となる重大なリスクには児童労働、強制労働、抑圧とハラスメント、差別、組合結成の妨害、最低賃金未達、虚偽報告などが含まれ、検出された場合は、直ちにその問題を是正することが求められます。また、労働環境マネジメントシステムの不備により発生する、残業代の支払いや法定休暇の付与、契約書の管理などにおける深刻な問題は、人権リスクが高く、十分なリスク管理体制が整備されていないことを意味するD評価に該当します。D評価に該当するリスクが検出された場合は、工場に早期の改善を促します。
• E評価の対象となる重大リスクの例*:
児童労働、強制労働、虚偽報告などの透明性に関する問題、未承認の委託先や家内労働者への外注、贈収賄・汚職、不適切な採用慣行(違法な人材斡旋業者の利用、外国人移住労働者に対する雇用手数料の払い戻しの未実施)、ハラスメントや嫌がらせに対する是正措置の不足、採用・賃金・報酬・研修機会・昇進・解雇または退職における差別的慣行、警報装置や消火設備などの緊急対応体制の不備、建物や構造物の安全性欠如、労働組合の結成が法的に認められている国・地域における結社の自由の欠如や結社の自由を妨げる慣行、最低賃金水準を下回る賃金支払い、賃金支払いの留保、違法な賃金控除、過度な長時間労働や過剰な連続勤務
*旧監査での「ゼロトレランス項目」に加え、連続勤務や情報の信頼性の問題などを追加することにより、従来より厳しい基準で工場の人権リスクを把握
• D評価の対象になるリスクの例:
児童労働を防止するための年齢確認体制の不備、雇用契約の不備、ハラスメントや嫌がらせ、労働者の安全に危険を及ぼす労働安全衛生違反、賃金および福利厚生の不十分な支払い
上記のほか、「生産パートナー コードオブコンダクト」に規定する幅広い項目が監査の対象となっています。例えば、労働者の健康と安全性、賃金と諸手当、長時間労働、苦情処理制度、女性労働者、外国人移住労働者、若年労働者、社会的少数者などの縫製産業のサプライチェーンに共通する社会的弱者への配慮などです。
労働環境モニタリングの結果に基づき工場を評価し、毎年結果を開示しています。労働環境モニタリング結果については下記をご覧ください。
 是正措置
是正措置
E評価の対象となる重大なリスクが検出された場合、もしくは、D評価の対象となるリスクが2回連続して定例アセスメントで検出された場合は、工場との取引見直しの可否を判断するため、企業取引倫理委員会に上程されます。同時に、工場と問題の解決策を検討し、是正が完了するまで状況を確認します。企業取引倫理委員会では、当該工場の経営・雇用状況も踏まえた審議が行われ、取引の見直しの可能性について生産部門に勧告します。その後のフォローアップ監査で問題の是正が確認されなかった場合は、取引停止となります。ファーストリテイリングは、取引の見直しや停止につながる重大な人権侵害が発生しないよう、工場とともに未然防止に努めています。
重大項目が検出された場合は、工場に早期の是正を促します。一定期間内にファーストリテイリングの従業員が工場を訪問し、工場に対して適切なマネジメントシステムの導入と徹底的な再発防止を求めています。次回の定例アセスメントで、問題の再発を防止する仕組みが構築されたことを確認します。
ファーストリテイリングのモニタリングプログラムマニュアルと生産パートナー向けガイドブックには、是正措置の実行プロセス、監査後の是正タイムライン、根本原因の分析方法などが規定されています。工場において問題を未然に防止するための具体策が確実に策定・実行されるよう、工場に対して、公正労働協会(FLA)の原因分析ガイダンスをはじめとするさまざまな資料提供や支援を行っています。全体の監査結果や特に指摘が多い項目については、各ブランドの調達関連部署や工場にも共有しています。
外注先工場の労働環境モニタリング
ファーストリテイリングは、「生産パートナー コードオブコンダクト」において、ファーストリテイリングの事前承認を得ていない工場への生産委託を禁止しています。縫製工場の定例アセスメントにおいて、承認を受けた外注先工場のみを使用しているかを確認しています。
縫製工場には、生産工程の一部を委託する外注先工場に対して第三者機関による監査を実施し、ファーストリテイリングから承認を得るよう義務づけています。外注先工場は毎年監査を受け、ゼロトレランス項目が検出された場合は、ファーストリテイリングと合意した期間内に是正し、再監査を受けて合格する必要があります。
労働環境モニタリング結果
新監査プログラムによる2025年8月期の縫製工場の労働環境モニタリング結果は以下のとおりです。
新監査プログラムにおける2025年8月期の縫製工場の監査では、深刻なリスクがあり、取引見直しの対象となる「E評価」は28工場となりました。主に連続勤務や情報の信頼性の問題が発見されています。これらの工場のうち、14工場の改善を確認し、ほか11工場は、改善や再発防止に向けて、対応策の実行に着手しています。また、残りの3工場とは取引を終了しています。
なお、2025年8月期は、監査プログラムの移行期のため、一部の工場では旧監査を実施しています。2025年8月期に旧監査の対象となった縫製工場は95工場であり、71工場では重大項目やゼロトレランス項目は認められませんでした。他方、「ゼロトレランスあり」の評価を受けた工場は4工場あり、確認されたゼロトレランス項目は長期間の連続勤務(1工場)の他、社会保険料の計算の誤りや労働組合に対する法定の工場拠出金の未納などの重大項目が2回連続検出されたことでした。この4工場とは、改善や再発防止について議論を重ね、うち3工場ではすでに改善されたことを確認しています。残りの1工場については取引を終了しています。
また、2025年8月期に実施した旧監査で「重大項目あり」の評価を受けた工場は20工場ありました。「重大項目あり」の評価を受けた工場で確認された主な重大項目は、残業代や手当の計算不備などの「賃金と諸手当」(指摘された重大項目の45%)、契約書の内容不備などの「採用・雇用」(同21%)、解雇手続きにおける不備や解雇に伴う退職金や賃金の未払いなどの「解雇プロセス」(同19%)、長時間労働や労働時間の管理不備などの「労働時間」(同10%)でした。すべてについて工場と改善計画を合意し、工場が改善に取り組んでいます。ファーストリテイリングの従業員が工場を訪問し、改善の進捗を確認しています。
そのほか、「生産パートナー コードオブコンダクト」の項目のうち、「健康と安全性」と「労働時間」に関する指摘事項が多く検出されています。問題の改善や予防に向けて、以下の取り組みを行っています。
 健康と安全性
健康と安全性
健康と安全性の領域で見つかる問題は、防火安全や労働安全衛生、化学物質管理など、多岐にわたります。これらに対し、生産パートナーへのトレーニングを定期的に実施し、現地法令やファーストリテイリングの労働安全衛生基準、ベストプラクティスなどを説明しています。また、工場に対して、問題への対処を求めると同時に、労働安全衛生の管理体制構築、防火対策や建物安全性の定期診断の導入といった、問題を未然に防ぐための仕組みの構築も求めています。サステナビリティ部の人権チーム(旧工場労働環境チーム。以下、「サステナビリティ部」)が工場を訪問する際は、防火設備の設置状況を確認し、問題がある場合は早急な改善を求めています。
また、ファーストリテイリングは、縫製工場におけるビルの崩壊や火災事故を防止するためのイニシアティブ「繊維・縫製産業における健康と安全のための国際協定(旧バングラデシュにおける火災予防および建設物の安全に関わる協定)」および「パキスタンの繊維・縫製産業における健康と安全のための協定」に署名しています。
関連リンク
 労働時間
労働時間
工場従業員の労働時間を定例アセスメントで確認することに加え、工場とファーストリテイリングの関係部署が協働して、工場における過度な労働時間の撲滅に向けて取り組んでいます。
工場は従業員の労働時間を削減するため、生産計画の立案方法を見直すと同時に、生産ラインの自動化、従業員のスキルアップトレーニングの実施、生産性と連動した報酬制度の採用など、生産効率の向上に取り組んでいます。長時間労働の発生が見込まれる場合は、工場には事前に生産部に連絡するよう依頼しており、生産部は可能な限り生産計画の調整などを行います。
ファーストリテイリングは、工場における労働環境を守り、工場従業員の人権を尊重するため、適切な手順に従って発注を行うことを規定した「責任ある調達方針」を策定しています。責任ある調達を推進するために、主要ブランドの調達業務に沿ったガイドラインも作成しています。主要取引先に対しては年次調査を行い、当社の発注が工場の労働時間の改善を遅らせるような過度な負担につながっていないか、ヒアリングを行っています。工場からのフィードバックは、生産部とサステナビリティ部で確認し、残業時間の根本原因を解決するための施策を検討します。
生産部は、主に縫製工場について、過度な労働時間が発生する根本原因を特定し、改善計画を策定します。その上で、毎月、工場の全従業員の週単位の労働時間実績を収集し、改善進捗を確認しています。
サステナビリティ部は、改善計画の進捗を確認し、必要に応じて工場を訪問して、労働時間の実績を確認しています。社内で定期的に進捗確認会議を実施し、工場の改善状況を共有しています。工場と密にコミュニケーションを取りながら改善状況を確認するとともに、労働時間が削減されることによって工場従業員の収入が損なわれないよう、賃金と福利厚生を維持する施策について他社事例の工場への共有などを行っています。
これまでの取り組みを通じて、多くの工場で長時間労働の改善がみられました。今後も、工場従業員の労働時間の適正化に取り組んでいきます。
関連リンク
労働環境モニタリングプログラムの改善
定例アセスメント結果を分析することで、労働環境モニタリングプログラムの効果測定を行っています。分析結果に基づき、労働安全衛生、賃金と福利厚生、労働時間などの重点領域における指摘件数の削減とスコアアップを目標として設定しています。
生産パートナーの従業員がファーストリテイリングに直接相談できるホットラインも設置し、アセスメント以外にも課題を特定する方法を導入しています。少なくとも年に2回、緊急度の高い課題、国や地域特有のリスク、高リスク工場の改善支援状況など、取り組みを通じて把握した傾向やリスクが経営陣に報告され、必要に応じて人権委員会やサステナビリティ委員会に上程されます。
上記およびFLAから得た意見や助言、また、ベターワークなど外部団体との取り組みなどの過程で得た気づきは、検討のうえ、プログラムの改善に反映されます。例えば、ファーストリテイリングホットラインに寄せられた意見を分析し、工場内の苦情処理メカニズムを強化したり、工場経営者が自ら問題を発見、調査、解決したりできるように労働環境モニタリングプログラムを改善しました。
さらに、国やブランドごとに、定例アセスメントの合格・不合格数や違反傾向を分析しています。こうした傾向分析とあわせて、主要な生産国ごとの課題を整理し、改善策を策定しています。各国の課題の優先順位は、ステークホルダーエンゲージメントの結果やビジネス戦略との整合を図りながら設定しています。